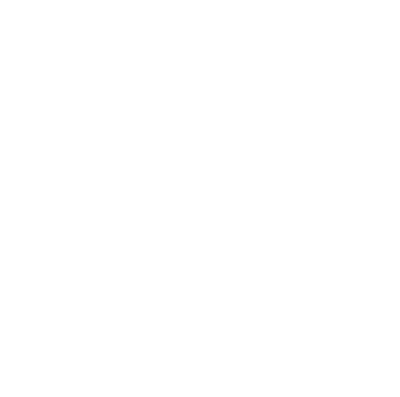「やっぱね」石田純一という存在のラブソング
きっと人生最後のデートだと思う。それを分かっている。
この物語をどこから話そうか。
何故、彼が青春のケロイドを剥こうとしたのか
何故、彼女にエレベーターの魔法がかかったのか
話をさかのぼる事、コロナ禍真っただ中の2020年、僕は一つの挑戦をしていた。
クラウドファンディングで「スタジオを作る、リターンは全員分のオリジナル曲」という例のヤツ。
そこに一人のミュージシャンから連絡がきた。
多田ルミエ。
彼女はYapani!というバンドの長であり、数々の剛腕なブラスバンドに在籍した現代の巴御前である。
僕のバンドP.O.PとYapani!は親戚のような関係性であり、2010年頃に僕らが在籍したTheCubesというビックバンドがP.O.PとYapani!の合体バンドであった。
気づけばヤパニも僕も平成を奔走する20代から令和に腰かけるオジさん&オバさんになってしまったが
なにはともあれ、その巴御前ことルミエが「ヤパニとのコラボ曲作ってもらうもあり?」と高額支援を投げ込んできた。
これが発端である。
Yapani!とは上鈴木兄弟や熱々小籠包が既にコラボしてたこともあり、待ってましたと二つ返事。
リリースの度にiTunesジャズチャート上位を獲得するJazzFunkブラスバンドと何をしよう。
想定した曲調は2つ
・キングカーティス+スティービーレイヴォーン=ブルースブラザースのような曲
・80〜90年代の横浜が匂うキラキラしたトレンディなブラコン
この提案に、持ち曲にメロウな曲がないから。と選ばれたのは後者。
作曲に取り掛かり、まず最初に決まったのが曲名だった。
「ヤパニとのコラボ曲、、んーどんな歌詞にするかなぁ、、ヤパニ、やぱに、やっぱに、やっぱね、、、やっぱね!!」
これだ。ストーリーは1ミリも浮かんでないが絶対にこれだ。
これ以上の命名はないと思った。
歌詞は、動いていると湯水のごとく湧き出て、座っていると出ない。肉体の構造上そういうもんだと思う。
正確にいうと景色が流れていると出るの方が近い。
歌詞を書くぞと愛車バモスが首都高に乗り込む。
頭に浮かぶ情景が次々に言葉に変わっていく。
やっぱね
首都高
20代からの付き合い
おじさんとおばさんになった僕とヤパニ
9thの響き、コーラスのかかったFMエレピ、タイムカプセルと化すゲートリバーブ 、、、
彼はもう一度ひとり分の生活に戻っていた
彼女の名字が変わっていることは風の噂で知っていたが人生の第3コーナーを前にあの日に何かを忘れてる気がした。
夢を追う体たらく、愛想を尽かした若き日の彼女、家を追い出されたあの日に。
連絡は取れた、名字のことは聞かなかったし、彼女もぼくの暮らしを聞かなかった。
待ち合わせ場所に君はいた。
僕は照れ笑いを浮かべながら助手席に誘い薬指を見ないふりをした。
完成したデモを送る。
メンバーも問題ないとのことで早速レコーディングに取り掛かる。
タイトルはもっとウケるかと思ったがややウケだった。
スタジオはハピネススタジオという僕らの界隈では有名なスタジオ。
そこの平野さんはAOR/シティポップの旗手、一十三十一のチームメンバーでもあるので今回の曲にこの上ないマッチングだ。
長い付き合いのバンドとの録音はスムーズに進む。
出来た。
サラッと完成した。
もはやレコーディングというより授業参観日のお茶会の様相で出来た。
スタジオからの帰り道、僕は思ってた。
自分でもすごく好きだ。この曲。満足してる。
クラファンでこんなオフィシャルリリース作品作れてラッキー過ぎるぞ俺。
この時はまだ、この後にどんな奇跡が起こるのか知る由もなく冬空を自転車で駆けた。
ホテルの車止めに誰も見たことない青のスポーツカーを止める。
見栄えを気にするタイプなのは変わらないのね。そんなところも可愛げがあったっけ。
他愛もない会話を途切れさせない特有の軽さに救われた気もするなと思いながら彼女は車を降りる。
昼下がりのホテル。ただその一文で説明は必要ない。2人は昼下がりのホテルに入って行った。
湿ったラブストーリーになど縁もない太陽のような男がZOOMに映る。
「飛べないスケートボード」をはじめ僕の数々のMVを作ってきたイッチイ(イチキロ)が今回も映像を作る。
彼を交えた三人は完成した曲を前に、
「なんか簡単でサクッとふざけたやつ撮っちゃおう」
「トレンディパロディとかでいいよね」
「あー、石田純一みたいな格好させたり、カンチみたいなやつねー」
なんつってダラダラしてた。
「あ、石田純一のHPにメールフォームあるわ」
「馬鹿なフリして依頼メールしてみようぜwww」
「無理だろwww」
「で、どうしよっかねMV」
こんな感じで何も決まらずダラダラと時は過ぎた。
二週間くらいたった頃だった。
「ヤバイ、話せる?ヤバイことが起きた」
なんだよと思いながら、更に追い討ちできた次の文章に即座にZOOMを起動する。
「石田純一からOKが来た!!」
ワザとらしく肩を抱いた。
滑稽なほど露骨なエントランスを通るにはそのまま歩くのが照れ臭かったから、茶化したフリを笑って欲しかった。
上下運動を繰り返すだけの箱が重力に逆らっていく。その様がまるで時間に逆らっているような気がした。
音のないタイムマシンが時の階層を登っていった。
本気のラブストーリーにしよう。
ここへきて石田純一が、ワイドショーのイロモノとしてではなく、役者として本気で演技をする。
それがいいと全員が思った。
だが、どうやっていいか分からない。
キャストも進行も、何よりそんな大きな主役を処理できる能力は僕らには到底なく頓挫は目前だった。
直ちに「さいとうりょうじ映画祭」の精鋭たちに連絡をする。
「あの、、また、、今年も、よくわからない騒ぎを起こしそうなのですが、あの、、お力をお貸しいただきたく、、」
「溺れる射手座の」藤監督に「Letter」のスタッフ陣、振り付けのピーター、「ごめんねソーリー」の衣装のチームの総動員。
あー、またこのターンが来たかと、いつもの呆れ顔と苦笑いでみんな付き合ってくれる事になった。
女優が決まる、かねてから僕と親交のあった今村美乃さんと藤監督推薦の平山さとみさん。ロケ地もビシバシ決まっていく。
プロのスタッフの凄さをまざまざと見せつけていく彼ら。これならどうにか完成できるかもしれない。
( 余談だが、実は今回1番僕らの財布を痛め付けたのはロケ地だ。インディーズのMVは大体がゲリラ撮影で行われる。
海、渋谷の線路脇、センター街、基本的に全部無料のゲリラ撮影でやってる。それで問題は起きない。
持ち主に情報が届くほどの規模じゃない事がほとんどだから。
でも今回はキャストに飛び火する事は許されなかった。向こうの炎に巻き込まれるなら願ったり叶ったりだが、こちらが新たな火種になる事は避けなければいけない。これ以上は純一も焦げてしまう。
だからホテルからちょっとした道端まで全て正規の許可を取り正規の使用料を払った。さすがに高かった。。。www )
気温は30度を越えセミが泣き始める。
またたくまに真夏の撮影日がやってきた。
早朝からの撮影に嫌な顔一つせずに本当にすごいという連絡が入っていた。
朝は都心での撮影、僕は昼の町田のホテルから合流した。
現場に着くと彼は本当にいた。本物が本当にいる。
このおかしな日本語は数年に一回僕の中で出てくる。
職業柄、著名人に会う事には慣れているが、それを飛び越えるような大物との邂逅で思う言葉が”本物が本当にいる”なのだ。
長身細身の圧倒的オーラ。全ての女性が虜になるスター。本当だった。
昼食の時間をとらずダンスの振り入れをしたいと言う。本物だった。
午後の撮影に入る。このMVのポイントの一つ「エレベーターのシーン」
アレを作るために難儀する現場。
廊下の幅は狭いから遮光の布を持つ人足が必要になる。
僕は黒い布を掲げながらうっすら見える向こうの2人に目をやった。
エレベーターのドアが開く。
上下運動を繰り返すだけの箱は本当にタイムマシンだった。
この味気のないホテルの廊下は現実と並行したあの日の世界線だ
今日の僕の前にあの日の君がいる。
青春のケロイドは水気を含んだ皮膚に戻り摩擦を求めた。
「演奏シーンは入れよう」
情事を演奏シーンで表現する。
ヤパニメンバーと俺、そして一瞬しか登場しないフルートを吹いただけの熱々小籠包が堂々の参加。
とにかく現実離れしたい。なぜならこれは現実ではなく情事の比喩だから。
仕込みは難易度を高めていく。
色、光、シャボン玉、、、そして衣装。
衣装はありものでは表現しきれず創作することになった。
これまでも要所で衣装協力をしてくれてきたチームに趣旨を説明したところ
そんなもん用意できないから作る。となった。
結果このシーンが作品に与えた影響は「一回目は熱々小籠包の腰の動きしか思い出せなくなる」であった。
男はどこまで行っても馬鹿である。
自分を通り過ぎて行った恋人たちをいつまでも恋人だと思っている。
石田純一氏も今回のコメントで「男の恋は一本道、女の恋は曲がり角。男はいつになっても振り返る」という筆を走らせている。
おざなりな夜景を向こうに彼が呟いた「やっぱさ」の言葉は彼女から表情を引き出す。振り返る直前のあの表情にこの曲の全てが詰まっている。
振り返る、何も答えず手を取る彼女、これで最後と。
そんなことより私と踊りませんか。ワン、ツー。
実は今回の監督のイッチィは、僕の昔のバンドのドラマーであり、内装補修職人であり皮職人であるが、なによりも
「踊ってみた」コスプレ部門というとても専門的な世界でランキングTOP10をほぼ総ナメにする名監督として知られている。
そんな彼がこだわったのは「石田純一を踊らせたい」
そりゃあそうだろう。そんなこと踊ってみた業界でも前例を見ない快挙になる。
振付師はP.O.Pなどこの数年ずっと一緒にやってきたピーター。
当日も本番までみっちり付きっきりで稽古をする。
大物にも関わらず嫌な顔せず空き時間に稽古をする主演俳優に勿論頭は上がらないが
この謎なシチュエーションと謎な重責を謎に背負わされたまま稽古をつけるピーターには本当に頭が上がらない。
真夏の日が暮れた。
早朝からの撮影は12時間を経過し役者の疲労が懸念され、ロケ地の制限時間は残り2時間。
スタッフ全員がわかっていた。この踊りのシーンが軸になる。
たまたま居合わせた人々が見物に群がる。
彼女が引いた手がフレームに入った。
咲いた花火がいつか散る様にかかった魔法はいつか解ける。
彼の言葉に振り返る前に、いや、この誘いを受けた時点で彼女はこの花火が散ることを知っていたし、二度と夜空に大輪を咲かすことがないことを知っていた。決めていた。
だからこそ彼女は手を引いた。最後の花火を上げるため、最後のデートを終わらせるため、もう二度とあなたを愛さないために。
繋いだ手が離れることを惜しんでいる。
視線は下から上に上がっていく。
魔法は全て解けた。
彼女が何かを言った。それに彼も返した。二人の言葉は僕たちには聞こえなかった。
最後のシーンの撮影が始まる。
監督と主演が車に乗り込んで夜の横浜を流す。
アウトロでの帰り道のシーン。
この曲は意外にアウトロが長いが監督の脚本には「純一の帰り道 運転」としか書かれていない。
このドラマの締めくくりは平成という時代を背負った稀代の男の演技に託された。
「全部OK!撮影終了!」
スポーツカーが戻ってきた。イッチイが声を張り上げる。
長かったひと夏のチャレンジが終わりを告げた。
全てのスタッフが充足と安堵に満ちている。
疲れと経験と楽しさがインパクトとなり駆け抜けた1日。
それらが終わりを迎えた。
完成してから僕は初めてその最後のシーンを見た。
みなとみらいを走り抜ける石田純一の表情。
涙が出てきた。
僕の書いた歌詞を、メロディを、演奏を、その真意たちを
なぜここまで汲み取ることができているのだろうか。
なぜここまで表現することができているのだろうか。
その表情それだけで。
この時にやっとわかった。
この曲はこの人のフィルターを通して初めて完成となる曲だった。
最初からそう決まってたのだと。
変わったのは僕だろうか、変わらなかったのは君だろうか。
変われなかったのは僕のほうか、変わってしまったのは君のほうか。
あの日のままの平行線を辿る道の上
すこし笑った顔をして「じゃあね」なんて言うからさ
すこし分かった顔をしてこう言うしかなかったじゃないか。
「やっぱね」